新書の帯には、「人はみな幸せになるべき なんて大ウソ!」と書かれている。
「え、なんで?」
このあたりを中心に、追ってみたいと思う。
どういうわけか、今日の日本では(そしてアメリカでも)「幸福論」が大はやりです。だいたい「幸福論」がはやるというのは、多くの人が何か不幸だと感じているからでしょう。その意味では、この時代は決して良い時代とは いえません。
「反・幸福論」p 13
| 書名 | 「反・幸福論」 |
| 著者 | 佐伯 啓思 |
| 出版社 | 新潮社 |
| ISBN-10 | 4106104504 |
幸福になろうとすればするほど、不幸になる仕組み
幸福になろうとすればするほど、どうやら不幸になってしまうという「法則」にわれわれも捉えられてしまっているようにもみえます。
「反・幸福論」p 13
われわれは、自由であり、平等であるべきで、自由を市場競争によって実現するのが当然のすがただと考える。自由な競争の中で財貨を稼ぎ幸せになる権利がだれにでもある。
(このような捉え方は「リベラリズム」と呼ばれている)
このような考え方をわたしたちはなんの違和感も持たずに受け入れているが、
「幸福」という言葉ほどわかったようなわからないような言葉はめったにありません。おそらくそれが何を意味しているのかはわからないのに、誰もが「幸福になりたい」と思っているのでしょう。いや、その程度の素朴な感情ならよいのですが、どうも現代人はそれより一歩踏み込んで、もっと積極的に「幸福であるべきだ」と考えているようです。「人は幸福でなければならない」という道徳意識さえもっているのではないでしょうか。言いかえれば、不幸であることはただその人がつらいというだけではなく、何か道徳的にもよからぬことであるかのようなのです。
「反・幸福論」p111、アンダーラインは筆者が追加
図式的に書くと、
「幸福になりたい」(ささやかな願い)
↓
「幸福であるべきだ」
↓
「人は幸福でなければならない」(倫理的要請に変容)
幸福になりたいというささやかな願いが、「人は幸福でなければならない」という「倫理的要請」に変容するあたりから、不幸へ向かう車輪 が動き出しているようだ。
「人は幸福でなければならない」(倫理的要請)
↓
「幸せ」でなければ「哀れみ」や「さげすみ」の目で見られる
↓
「わたしはちゃんと幸福ですよ」
ということを「示さなければ」ならない
なにせ「倫理的要請」なので、「わたしは倫理的に正しい」ことを「まわりに向かって」示さなければならない。まわりから認めてもらわないと村八分になりやしないか?という不安がつきまとう。
「あいつは不幸そうだな、けしからん!」などという自衛監視集団すら現れかねない。
もう、自分が幸せかどうかの問題ではなく、他者からの承認を得ることこそが重要になってくる。
しんど。
他者から「あなたは確かに幸せです」という承認を得るには、財力や地位や名声など、わかりやすい評価基準(つまり「社会的成功」)が適用される傾向にある。
「幸福」=「社会的成功」という暗黙の共通認識
↓
「財力や地位や名声」(=「社会的成功」)が倫理的に要請される
浅い価値観に満ちた文化の中で、私たちは、運転する車、着る服、通う学校によって人を測定するように教えられてきた。あまりにも多くの人が、明白で表面的なことに目がくらみ、物事の核心を見る常識と忍耐力を欠いている。
出典:Madeline Levine, “Challenging the Culture of Affluence”, NAIS, 2007、筆者訳
これだけ「自由」がもてはやされている世界に住みながら、「社会的には成功しているとは言えないかもしれないけど、わたしは十分幸せですからほっておいてください」という自由はなさそうだ。
「幸福」=「社会的成功」という暗黙の共通認識
↓
幸福の基準がいつも他人との比較
↓
だれもが社会的に成功するわけではない
↓
幸福への条件が平等になっていないからだ
↓
「違い」=「不平等」
↓
不平不満の連鎖
もちろん「不平等」をなくす取り組みは重要とみなされ広くなされてきた。
そして完璧ではないにしろ、みなに平等な「自由」や「権利」が与えられている。
だとすれば、
「人は幸福でなければならない」(倫理的要請)
↓
「不幸な人は幸福になる努力を怠っている」
↓
「弱者救済」は弱者のためにならない
↓
「格差を是認」
なんて「つめたい世界」なんだ。
日本の状況
大体においてアメリカのしっぽを追いかけている日本では、こと政治哲学関しては、90年代を通じて、個人の権利や個人の自由に絶対的な価値を置くリベラリズムが優勢でした。おまけにそこに構造改革を唱える市場原理主義が加わり、ますます個人主義、自由主義、能力主義へと傾斜していきました。
「反・幸福論」p18-19
企業組織は集団主義として批判され、家族はもはやかつてのように食卓を囲む家族団薬などということはなくなり、大店法や宅地開発、大都市への人とカネの集中によって地城は崩壊してゆきました。さらにグローバリズムやボーダーレス化という掛け声のもとに国家の権限は著しく弱体化し、まとまった国民的な価値などというものはどこを見渡しても見失われてしまったのです。これが「構造改革の成果」だったのです。
この記事の趣旨から外れるので具体的な話題に触れることは控えようと思うが、バブルの崩壊の頃から日本の状況もおかしくなってきていることを強く感じる。
おわりに
だが確かなことは、「自由」を求め、「利益」や「権利」を増大させることで「その先にある幸福」を手にできると見なしてきた戦後のわれわれの生き方そのものにもはや信を置くことができなくなっているということなのです。
「反・幸福論」p36
タワーマンションに住み、高級レストラン似通うような人が「勝ち組」として羨ましがられ称賛され、貧乏生活の人は「負け組」とみなされ蔑まれる残酷なヒエラルキー。かつて存在したであろう「清く正しく美しく」粛々と生きていく、そんな生き方を良しとする感覚は近年ますます失われていった。
こんな「つめたい世界」で生き残るため、「あなたはちゃんと幸福ですね」という承認を得るため、「他者との比較」である以上「皆が幸せになる」なんてことはあり得ない世界の中で落ちこぼれないように、身を粉にして神経をすり減らしながら今日も働くのであった。
おかしいですよね、こんな世界。
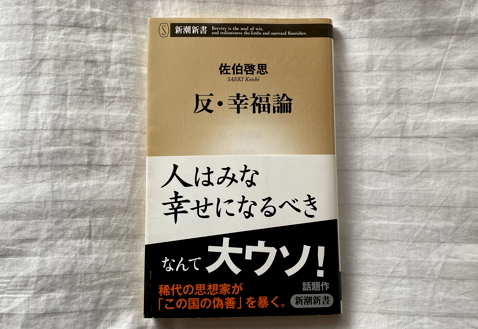


コメント