
デカルトはいうまでもなく高名な哲学者であるが、この「方法序説」は、哲学書というよりも自叙伝だ。
なので、哲学的含意をあれこれ議論するのではなく(わたしにはその力もない)、たんに「頭の切れる先輩のお話を聞かせてもらう」という感覚で読んでみる。
(哲学的な何かを期待して来てくださった方には、申し訳ない!)
ちなみに、書物の本来の名称は、
「かれの理性を正しく導き、もろもろの学問において真理を求めるための方法の序説、なおこの方法の試みなる屈折光学、気象学および幾何学」ながっ!
| タイトル | 方法序説 |
| 著者 | ルネ デカルト |
| 出典 | 岩波文庫、落合太郎訳、第43刷 |
| 著作発行年 | 1637 |
著作の意図
本書は、次の有名な一節から始まる。
良識はこの世のものでもっとも公平に分配されている。
第一部 p12
良識 (bon sens)とは、理性(raison)ともよばれ、「真実と虚偽とを見わけて正しく判断する力」のこと。
「正しく判断する力」が「公平に分配されている」?
のっけから置いてけぼりをくらいそうになる…
理性あるいは良識が私どもを人間たらしめるもの、私どもを動物と区別する唯一のものであるかぎりは、それは完全にひとりびとりにそなわると私は考えたい。
第一部 p12
どうやら、「動物と違って、人間なんだから、みな理性=良識=判断力を持っているといえるよね」、ってことのようだ。出発点として。
理性はだれもがもっているとすると、次に必要なのは「それを正しく導く方法」である。
その方法について説明したい、だから「方法序説」。
わたしの考えでは、「何かを成し遂げる」= 努力 X 能力 X 方法。
デカルトは、「努力」については言及していないけど。
そこでデカルトは、自身のとった「その理性を正しく導くため」の方法について、
「一つの寓話くらいなもの」として示したいという。教えようとするのではなく。
書物による学問
デカルトは、幼い頃から優秀で、当時の「書物による学問」は、
幼少の頃から私は書物による学問で育てられた。
↓
人生の役に立つと信じ、どこまで熱中した。
↓
あらゆる学問に精通した。
↓
でも、自分の無智を発見していったということを別にすれば、なんの利益をも受けなかったと思われるほど、はなはだ多くの疑問と謬見に悩まされた。
諸国語も、雄弁術も、神学も、数学も…
数学は機械的な応用技術にのみ仕えるものと思いがちであったが、それの根抵がきわめて堅牢でありきわめて確実であるのを知ると、この上になお一層高いものが何一つ建てられていないのを見て私は驚いてしまった。
第一部 p19
哲学については、…
第一部 p19
真なるべき意見はただ一つしかありえないにもかかわらず、いかに多種多様な意見が学識ある人人によって主張せられうるものであるかを見、真実らしく思われるにすぎぬような事はすべて、ほとんど虚偽なるものと看做したということ。
そんなわけで、大学卒業とともにデカルトは、「書物」による学問をやめ、実践的な「世間という大きな書物」から学ぶため旅立っていく。
おのれになんの影響も与えぬ空理のために、学者たちが書斎であやつる推論においてよりは、一つ判断をあやまればすぐに処罰されねばならぬ結果をきたすような、おのれにとって重大な事のために各人がこころみる推論においてこそ、はるかに多くの真理に出会うことができようと思われたからである。
第一部 p20
旅先にて
よその人たちの風習を眺めることだけしかしなかったあいだは、色々な風習や考え方があるんだな、程度しか学べなかった。
最大の収穫はといえば、
第一部 p21
私どもにとってこそ甚だ異常なあの笑うべきものに思われても、他の処処方方の大民族によっては一般に受けいれられ、是認される多くの事のあるを見、単に実例と慣習だけで自分を承服させてきたような事はこれをあまり堅く信じすぎてはならいと覚ったことである。
でもこれ、結構重要で、色々な風習や考え方があるんだな、程度なら害はないが、風習や考え方の違いで論争や紛争が発生することを考えると、じゃあどっちが正しいの?となる。
それに答えを出そうとするのが哲学をはじめとする学問かもしれない。
さて次に、ドイツで戦争に参加するのだが、戦争といっても現代のイメージとは程遠く、ドイツの田舎町で、だれにも邪魔されず思索にふける時間があった。
そこで得られた思索の最初のひとつは、
いくたりもの棟梁の手でいろいろと寄せ集められた仕事には、多くはただひとりで苦労したものに見られるほどの出来ばえは無いと気づいたことである。
第二部 p22
多くの人の意見で少しづつ組み立てられてきた学問なんかより、秀でた一人が進める単純な推論のほうが真理に近づけるのだ。
デカルトの眼には、政治や社会、学問や教育体系など現在あるものはみな、誤謬に満ちたばかばかしいものに見えたのだろう。デカルトには、自分ならもっといいものにできるのに、と思えただろう。
そうなのだ。(デカルトならできる!)
そうなのだけれども、デカルトは思いとどまる。
ある国家をその根抵からことごとく変えるとか、学問全体の組織や学校の秩序を抜本改革するとかは、一私人にはどだい無理なはなしだ。そう自分に言いきかせる。
大組織は不完全なものだけど、慣習がまことにうまく緩和してきたのである。
それは智力をもってしては、慣習が作用するほどに、それほどよく工夫できるものではない。
とかいいながら。
私の計画は、私自身の思想を改革することにつとめ、すべて私自身のものである基礎の上に私自身の思想を構築するというにとどまり、決してそれ以上には出なかった。
第二部 p26
世の中はかような事にどうしても向かぬ二種類の人たちのみでおおかた成りたっている、とデカルトはいう。
- 自信過剰で、急いで自分の判断を下さずにはいられず、考えを順序よく導くために十分な忍耐を持たぬ人たち。
- 自信がなく謙虚で、有能な誰かの意見に従うことに満足する人たち。
いや、その前に、もう一つ重要なカテゴリーがある。
「世の中がまちがっていることを知りながら、何も行動を起こさないこと。」
そう、デカルトは積極的には行動を起こさなかった。
ガリレオがカトリック教会から有罪判決を受けたような時代である、無理もない。
無理もないのだが…、人間デカルトの葛藤が、行間に見え隠れしているように思う。
「その理性を正しく導くため」の方法
そうこうしているうちに、「その理性を正しく導くため」の方法として、デカルトは4つの格律にたどり着いた。
第一は、明証的に真であると認めることなしには、いかなる事をも真であるとして受けとらぬこと、すなわち、よく注意して速断と偏見を避けること、そうして、それを疑ういかなる隙もないほど、それほどまで明晰に、それほどまで判明に、私の心に現れるもののほかは、何ものをも私の判断に取りいれぬということ。
第二は、私の研究しようとする問題のおのおのを、できうるかぎり多くの、そうして、それらのものをよりよく解決するために求められるかぎり細かな、小部分に分割すること。
第三は、私の思索を順序に従ってみちびくこと、知るに最も単純で、最も容易であるものからはじめて、最も複雑なのの認識へまで少しずつ、だんだんと登りゆき、なお、それ自体としては互になんの順序も無い対象のあいだに順序を仮定しながら。
最後のものは、何一つ私はとり落さなかったと保証されるほど、どの部分についても完全な枚挙を、全般にわたって余すところなき再検査を、あらゆる場合に行うこと。
第二部 p29-30
この辺りが、「中世的迷妄主義からの独立宣言であり、近代精神の確立を告げる画期的なものであった。」(岩波文庫、帯)のゆえんなのだろうか?
この格律は、物理現象を相手にする研究開発においては、今も妥当する。
技術部門に配属される新人に対しての必読書にしたいくらいだ。
ここまで(第三部)の内容は、理系のわたしにもよくわかる(わかった気になれる?)。
デカルトは、頭の切れる理系畑の大先輩に思える。
さらにデカルトは、生活はできるだけ幸福につづけてゆき、自分の日日の行動にかぎっては不決断におちいらぬようにと、デカルトは自分のために当座の準則を作る。(これは蛇足?)
- 宗教をつねに守りながら、国の法律および慣習に服従してゆこうということ。
よい子でいる方が幸福。 - 一たびそれとみずから決定した以上は、どこまでも忠実にそれに従うということ。
- 運命よりはむしろ自分にうち勝とう、世界の秩序よりはむしろ自分の欲望を変えよう、と努めること。私どもの権力の埒内にそっくり有るものは私どの思想だけであるから。
- この世の人人の営む雑多な仕事に眼を通し、そのうちから最前のものを選ぶ。
すなわち、上記方法に従って力のかぎり真理の認識へと前進すること。
我思う、故に我あり
「明証的に真であると認めることなしには、いかなる事をも真であるとして受けとらぬこと」
これを実践に移すと、
いささかでも疑わしいところがあると思われそうなものはすべて絶対的に虚偽なものとしてこれを斥けてゆき、かくて結局において疑うべからざるものが私の確信のうちには残らぬであろうか、これを見とどけなければならぬと私は考えた。
第四部 p44
感覚もダメ、幾何学もダメ、自分の内の思想もダメ…
そのように考えている「私」は必然的に何ものかであらねばならぬことに気づいた。
第四部 p45
そうして「私は考える、それ故に私は有る」というこの真理がきわめて堅固であり、きわめて確実であって、懐疑論者らの無法きわまる仮定をことごとく束ねてかかってこれを揺るがすことのできないのを見て、これを私の探求しつつあった哲学の第一原理として、ためらうことなく受けとることができる、と私は判断した。
お待たせしました!
すべてを疑ってしまうと、思索を組み立てる土台までも壊れてしまう。
きちんとした建物を建てるには、確固たる基礎石が必要なのだ。
デカルトがようやく見つけ出した基礎石が、「疑っている自分は有る」。
わたし(技術者です)も、いっとき「懐疑」に襲われたことがあった。
方法的懐疑ではなく、状況的にすべてが信じられなくなった。
いままで組み立ててきた自分の論理が、どこかで間違っていたのかもしれない。
どこかで解釈を誤ったのかもしれない。
用いている測定器にしても、十分に校正していたつもりでも、どれかが狂っているのかもしれない。
「わたしが間違っているというならそれでもいい、本当のことを教えてくれ!」
苦悩の時間を経てわたしのたどり着いた場所は、「とりあえず高校物理Ⅱまでは信用するか。」
エネルギー保存則を、心の底から信じているわけではない。(たとえばの話)
信じてはいないけど、エネルギー保存則は、長年研究者などによる追試験に耐え抜いてきた理論だ。
将来それを覆す反証事例が報告されるかもしれないにしても、そのような事象が、この小さなわたしの研究室で顕在化するとも思えない。
だから暫定的に高校物理Ⅱまでは受け入れてみることにした。
信じられる基礎ができれば、あとは楽である。
ゆっくりでいいから、ていねいに一つづつ論理を組み立てていけばいい。
デカルトは、「我思う、故に我あり」という確固たるよりどころにたどり着いた。
自分が真理を語っていることを私に保証するところの「私は考える、それ故に私は有る」という命題のうちには、考えるためには存在しなければならぬことを私はきわめて明白に見る、ということ以外には何ものも無いことをみとめたので、私どもがきわめて明白に、きわめて判然と、概念するものはすべて真だということを一般的規則とすることができると考えた。
p46
ん?
すべてを疑え、といったあとで、「明白判然と概念するものはすべて真」とはなにごとか?
そのあとの展開が、わたしにはついていけない。
議論の中心に「神」が出てくるのだ。
神という名の、全知全能の実体のことを知的に理解した上で、その理解を通して議論を展開していくが、デカルトがどのように思ったのか、正直わからない。
しかし多くの人が、以上の事を知るにも、また自分の精神が何であるかを知るにも、相当の困難があると思いこんでいるわけは、かれらがかれらの精神を決して感覚的なもの以上にまで高めないためであり、またこれは物質的なものに対するかれらの特殊な考え方であるが、かれらはそれを構像することによってしか考えぬということに慣れきっているので、構像しえないものはことごとく、かれらにとっては理解しえないものに見えるがためである。
p50
わたしには正直わからない。
むりに解釈することもできなくはないが、そうしたところで単にわたしの主張を投影しているに過ぎない気がする。神の存在証明?
いずれにせよ、「その理性を正しく導くための方法」として問題となるのは、「明白判然に、私の心に現れるもの」の基準をどこに置くか?ということ。
敬虔なデカルトは、彼の信じる「神」の概念で彼の基準に到達した。
わたしは、神を信じないのだから、わたしなりの基準をわたしなりのやり方で見つける他はない。
わたしの場合は、「高校物理までは疑わないでおこう」だった。
「その理性を正しく導くための方法」としては、そういうことだと思う。
おわりに
デカルトは第六部のなかで、思弁的学問や道徳上の問題に関しては、それほど述べるべきものはないが、自然学的概念は、人生のためにきわめて必要な知識に達することが可能と知り、ここで知り得たことを公にすることは、使命であると語っている。
残念ながら彼の具体的な科学的・医学的成果は、いまとなっては色あせてしまったが、彼の採用した「理性を正しく導く」ための規律は、自然学にかかわる者たちのあるべき姿として現在でも妥当する。
デカルト先輩の話を聞きながら、わたしはそんなふうに考えた。

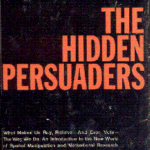

コメント